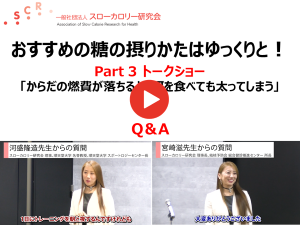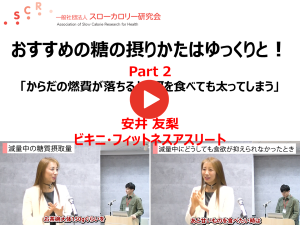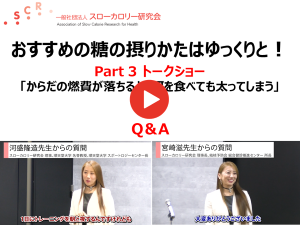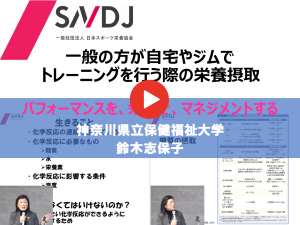おすすめの糖の摂りかたはゆっくりと!
安井 友梨さん
ビキニ・フィットネスアスリート
●FBB世界フィットネス選手権 優勝
●アーノルド・クラシック・ヨーロッパ優勝
●JBBFオールジャパンフィットネスビキニ選手権大会2015年〜8連覇中
●アジアビキニフィットネス選手権 優勝
Part1 「糖質の摂りかたを見つけ出し、世界で戦えるようになった!」
30歳になった頃にボディビルを始め、10年間で世界の頂点に上りつめた実績をバックボーンとして、安井さんはご自身の体重管理のエッセンスを、惜しげもなく公開されます。
ボディビルダーの食事と聞くとタンパク質(プロテイン)が第一と思われがちですが、今は「糖質をいかに摂るかが最も重要」と言われているそうです。安井さんも今は1日に白米1kgを食べているとのこと。ただし、3食ではなく5食に分け、かつ、冷ましてからタンパク質食品とともに食べ、そうすることで食後の血糖上昇を抑えられて、体重も増えないそうです。
そんな安井さんもかつては糖質制限をした時期があり、その頃、体重はなんとか管理できても体温が下がって肌が荒れたり、情緒が不安定になり、結局長く続けられず「糖質の重要性に気付かされた」と話します。その後、ダイエットと両立可能な糖質の摂り方を見つけ出し、それができるようになった頃から世界で戦えるようになったとのこと。白米でも品種によって血糖値への影響が異なることや、糖質食品でも麹を加えると血糖値が上がりにくくなることなど、ほかでは聞くことのできないダイエットの秘訣満載の講演です。
(収録時間09:59)

Part2 トークショー「からだの燃費が落ちると、何を食べても太ってしまう!」
続いて、国内パワーリフティング千葉県大会で優勝経験をもつ、DM三井製糖株式会社の久保宏樹氏の進行によりトークショーが行われました。
体重別階級のある競技の参加者は大会前に減量を行うことが多く、その際の食事の摂りかたが最初の話題。安井さんはオフシーズンは白米を1日5回に分けて食べているそうですが、減量期に入ってもそんなに量は変わらないとのこと。もちろんそれにはさまざまな工夫があるようで、そのあたりのテクニックまで掘り下げられます。
次の話題は、一般の方へのアドバイス。一般の方がダイエットをするときも、糖質は1食に最低150g必要であり、それより少ないとからだの燃費(代謝)が落ちて、何を食べてもすぐに太ってしまうと安井さんは語ります。そのほかにも、空腹感を我慢できない時にはどうするか、高甘味度甘味料とスローカロリー素材の違いは何かなどについて、安井さんの経験に基づいて語られました。筋トレやダイエットの実践者には気になるトピックばかり。(収録時間12:44)
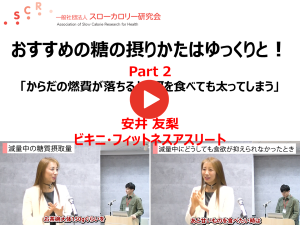
Part3 トークショー Q&A
トークショーに続き、講演会に参加した栄養関連の専門家とのQ&Aが行われました。最初の質問は河盛隆造先生(順天堂大学大学院スポートロジーセンター長)です。河盛先生は、安井さんは、ブドウ糖を全身の細胞が上手く使って強力な筋肉を作っている、安井さんの栄養摂取は理にかなっていると驚きます。そして、1日どのくらいのエネルギーを消費しているのかと質問しています。
次に、鈴木志保子先生(日本スポーツ栄養協会 理事長)は、糖質が重要という安井さんの話を聞いて、ボディビルも健康を考えたスポーツとして発展しているとコメントしました。
最後の質問は、安井さんがどうしても空腹を抑えきれないときに食べている豆腐について話題。全国から取り寄せているという安井さんのおすすめの豆腐を知りたい方は、ぜひご覧ください。(収録時間06:21)